

墓 地 死んだ人を葬って墓を建てる場所。 「大辞林 第二版」 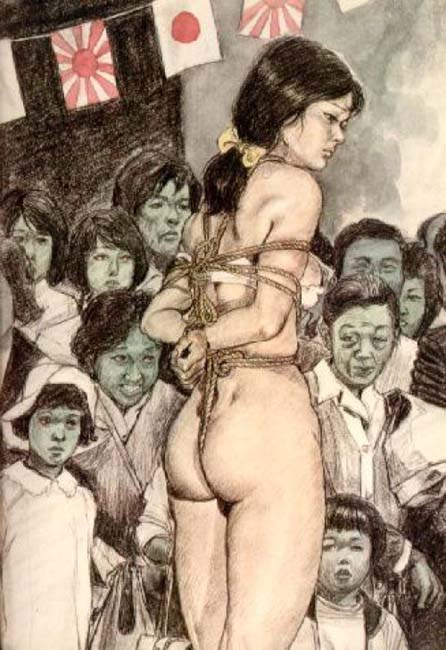 図書館と墓地は相似である……このように言うことは、冒涜であろうか。 冒涜だとしたら、何に対しての冒涜となることだろうか―― 図書館という建築物そのものに対してか、図書館が保管している蔵書そのものに対してか、 図書館という権威を擁護している人々の意識そのものに対してか、或いは、そのすべてについてか……。 ことさらに、反感、反発、批判、非難、嫌悪、憎悪を招くような発言は、 熟慮して最初から行わないようにした方が人間関係は円滑に進むことに違いない。 だが、言わずには済まないという事柄もある、激しく恋慕する相手に<好きだ>と告白する心情に似ていて、 <図書館と墓地は相似である>と……。 もっとも、図書館というものが存在理由としてあらわす、 <人類の偉大なる歴史的蔵書が示す叡智と審美の殿堂>という認識をそこへ入る者が抱くかどうかに関わらず、 そこは、自由に借りられる排泄場所、居眠り場所としては、清潔と静謐が適度に整っているのである。 この点では、墓地に比べて優るものがあるが、 交接場所としては、まったく逆転していることである―― 妖美とさえ言える黒の艶めかしさがそこはかとない白の純潔の色香を漂わせている、 喪の着物姿の若い未亡人に発情させられた義父が思い余って、立ち並ぶ墓石と卒塔婆の影に相手を押し倒し、 嫌がる女の綺麗な唇を無理やり求め、はだけた裾元を強引にたくし上げて悩ましい太腿をあらわとさせ、 おまえを愛していたのは、亡くなった息子以上に、このわしだったのだ、と叫びながら、 やり場はもはやそこにしかないという赤々と反り上がった怒張を押し入れる、 若い嫁も、一家一族の権威者の振舞いには、逆らうだけ立場を悪くするのはわかり切っていた、 子供がなかったことが幸いだった、涙のしずくを目尻に落しながらも、女の蜜のしずくをあふれ出させるのだった、 仕方がないわ、女ですもの……。 死者に小便を引っ掛けることは冒涜であるが、新たな生命の誕生を前提とする精液の放出は慰謝か希望のようだ。 図書館と墓地の相違は、<似て非なり>と言うには、外見がそもそも相違しているのであるから、言い難いことである。 その上、この相違を決定付けている事柄がさらにある。 墓地は相応の年数が経過したものであれば、暴かれることに考古学的意味合いが生まれるものであるのに対して、 図書館は、どれだけ年数が経過したとしても、蔵書を暴くという意味は、新たな発見を撚り合わせる未来学的意味がある。 従って、<図書館と墓地は相似である>、このように言うことを冒涜であると考えるとしたら、 それは、図書館への愛着と認識を欠いた者の発想ということになるであろう…… と言うのも、図書館と墓地が隣接している場所があり、それを眼前とさせられたとしたら…… 開かれた双方の入口に戸惑うばかりのことではない、その対比の迫真力に、言葉は失われるに違いないからだ。 あるのは……図書館と墓地は実はひとつである、という相反と矛盾の並置の収拾…… いや、そればかりのことではない、 恐らく、図書館のなかに墓地があるという場所はあり得ないことかもしれないが、 墓地のなかに図書館があるという場所は存在するかもしれないのだ。 東京は広い、いや、日本は広い、 いや、各自の因習に生きる数多の民族の棲息する世界は確実に広いのである。 <図書館と墓地は同一である>という認識に立った場所があり得ても、まったく不思議のないことである…… 人気の途絶えた真夜中の図書館…… それも、国立図書館のような膨大な歴史的蔵書を保管する広大な場所…… そこへ立たされたとき…… ひしひしと伝わってくる奥深い薄闇の静謐が広大な墓地の静寂と同様の暗澹とした感慨を抱かせ、 ずらりと並んだ書籍の背表紙が立ち並ぶ墓石や卒塔婆の碑銘と同様なものとして浮かび上がってくるとき―― そのなかで…… 現存するわが国最古の歴史書である『古事記』のなかに、 <まぐはひ(交接)><上通下通婚(親子婚)><馬婚、牛婚、鶏婚、犬婚(獣姦)>などはあっても、 <生まれたままの全裸を自然の植物繊維で撚った縄によって緊縛された女>の記述は、 何処を捜しても見当たらない。 従って、民族の創始である、 「毛むくじゃらの若者が白く美しい生き物から霊感を得て、縄を操ることによって国を興した」 という事柄は、まったくの作り話と言うことになる。 文書で言うならば、偽造文書と言うことである。 ある事柄が言語概念として述べられて、それがそれ以前の過去の言語概念において立証し得ないものであれば、 作り話か、偽造文書という可能性があるということである、 或いは、人間の想像力の醍醐味と言うことであれば、文学、文芸という絵空事である。 最古の歴史書の以前に発見される最古の文書があり得ない限り、 『古事記』があらわしている事柄は、民族の創始を記述していることを肯定も否定もできないものとしてある。 従って、権田孫兵衛老人は、<民族の予定調和>などと簡単に言っているが、 過去において立証を求められないものに未来の何が言い切れると言うのであろう。 だが、権田孫兵衛、その信奉者からは、大層にも<導師様>と呼ばれている老人は、 いとも簡単に言い放つのであった―― それ以前の過去に立証の得られないものであれば、 その示される言語概念こそが未来を実現する民族にとっての最古のものであることを立証すればよい―― つまり、現在語られている言語概念から民族の歴史は始まる、ということである。 問題は、いったい何なのか、民族の正当な過去なのか、それとも、正統な未来なのか。 言うまでもなく、その両者が必要とされることに違いないわけだが、 <民族の予定調和>というものが日本が沈没するような民族終末の危機意識をあらわすものとしてあるならまだしも、 <人間の抱く想像力こそが人間本来のものとしての神であるというヴィジョンを実現すること>というものである。 自覚として目覚めることであれば、格別に民族の創始から始めなくても、何時何処から始めてもよいことは事実であろう。 実際、これを読んでいる方々は、できることならば、みずからの存命中に起る事柄が望ましいと思っていることのはずである。 立証も難しい遥かな太古、起り得るかもわからない遥かな未来…… それらは、絵空事であるならば絵空事として、むしろ、娯楽性に富んでいる方が好ましいのである。 もっともらしくあって娯楽性に富んでいることであれば、切実な生活という因習をむしろ一時でも忘却できることがある。 切実な因習という生活を想起させ、立証を立証のために語られる整合性を求める言語概念など、 文書として墓地へ葬り去って置く方が無難であるかもしれないのだ。 それに比べれば、あたかも因習を脱却しているかのように生活臭さを滅却させて、 言語概念を言語概念の整合性において、疑問から答えを導き出そうとする形而上学の純潔としたありようは、 まるで、<女性の陰部>の語から、いまだに実際に見たことのない<おまんこ>を熟考妄想するような探求であり、 現代において、哲学が廃れたようになっているのは、 <女性の陰部>は<おまんこ>として、簡単にインターネットで画像が見れるからではないのだろうか。 見ることの可能な娯楽性に富んでいれば、ことさらに、見ることのできない言語概念は必要とは感じないのである。 物語も、映画に筋立てを提供できるような程度の文章力があれば、小説と称されて文学賞に輝くのである。 そもそも、小説や文学の定義が営利を目的とした企業の側で行われていることであるのだから、 経済を活性化させる産業が棲息している民族の生活を維持させている現実をあらわすことでしかない。 従って、言語概念の探求などというのは、もはや、異常性欲者の自慰行為に匹敵することであるかもしれない―― だから、ポルノグラフィなのではないですか―― そのような言語記述であっても、誰の眼に触れることがあり得なくても、 少なくとも、図書館の書架に安置されて、供養されることだけは間違いないであろう……。 だが、文書の事態はどうあろうと、権田孫兵衛老人が発語する<民族の予定調和>は進行している―― これは、否定できない墓地の現実であった。  図書館の広々とした閲覧室の開かれた窓の向こうには、黄昏が待っていた。 昼がまだ昼としての終わりを告げたわけでもなく、夜が夜として完全に始まったわけでもない、 光と闇が交錯する薄闇が支配する時間と空間があった。 その地平には、累々として立ち並ぶ多種多様の墓石が一面に広がり、 彼方の日没の一線まで果てしなく続いていた。 生を持って蘇ることは決してないが、厳然と子孫のなかに因習として存在する、 無限数の祖先という死者が眠り続けているのだった。 その窓辺にたたずんで、小夜子は、茫然とした面持ちで光景を眺め続けていた。 生まれたままの優美な全裸を麻縄で後ろ手に縛られ、綺麗なふたつの乳房には上下から挟まれた胸縄を施され、 艶やかな首筋から縦へ下ろされた縄がそれらを締め上げて、愛らしく突き出すような具合にされていた、 縦縄は、さらに、艶めかしい腰付きの女らしい曲線をあらわすくびれへ巻き付けられて、 可愛らしい臍のあたりから、なめらかな下腹部へ向かって下ろされているのだった、 その縄を掛けた女性が<私との離れられない結び付き>と言った、 思いの込められた股縄が漆黒の艶やかな恥毛を分け入って、女の割れめ深くへと埋没させられているのであった。 望むと望まないに関わらず、全裸を緊縛された縄は、 官能を煽り立てられる思いへと向かわせるものでしかなかったのだった。 小夜子の美しい顔立ちが茫然としているようであったのも、 ただ、相手からされるがままになることに、少しでも、かたくなになることができたら、という女の意地…… ささやかな抵抗のあらわれであったのだった。 だが、高ぶらされる官能の甘美に疼かされる浮遊は、眺めている広大な墓地に幻像さえ見させるものがあった―― ふたりの全裸の男は、抱きかかえた緊縛の女の生まれたままの裸身を彼方の日没の一線へ向けて運んでいた、 ゆっくりとした足取りで、黄昏の薄闇のなかを歩き続けていくのであった、 それは、長い、長い、長い時間を遡及する運行であったかもしれないし、 或いは、死者が執り行う行為としては、 一瞬のうちに空間を移動するようなものであったかもしれなかった…… やがて、広大無辺の墓地を抜けた先へ、その姿は消えていくのだった―― 「……小夜子さん、何がご覧になれて?」 彼女を緊縛していた縄尻を取る女性が優しく問い掛けていた。 小夜子は、すねて見せるように、振りかえることもせず返事もしないで、墓地の光景を眺め続けているだけだった。 「私と行ったこと、後悔なさっているの? でも、そうなることは、必然ではなかったのかしら? あなたと私は、すでに出会ってしまったのですから……」 小夜子は、緊縛で突き出させられた華奢な肩越しに、おもむろに振り返った。 そこには、顔立ちが恐ろしく自分と似ている相手が黒眼がちの深い陰翳のあるまなざしで見返している。 一之瀬由利子という、亡くなった夫の古い知り合いであったが、 そのときは、坂田由利子と名乗っていた。 どちらが本名であるのか、不思議に思わされることであったが、 いずれの女性にしても、しっとりとした穏やかで落ち着いた喋り方や振舞いは優雅でさえあったが、 有無を言わせない超然とした威圧感があることも変わらないことだった。 以前、一度自宅へ訪問を受けただけの相手であったが、突然、電話連絡がきて、 是非とも見せたいものがあるから、国立図書館まで足を運んでもらいたいと求められたのだった。 小夜子には、断ることのできない申し出であった…… 言いなりになってしまう、されるがままになってしまう…… しかも、それがまるで自然なことのように思えてしまう…… 不思議にも、惹き込まれていってしまう相手であったのだ、会うことには不安を感じるものの、 それは、未知への期待のように、甘美に胸を高鳴らせる感じが秘められているのだった…… ちょうど、とぐろを巻いた麻縄を見せられただけで、ときめく官能を意識させられるような擾乱があったのだ…… 解かれた縄は、再び、結ばれ、縛られ、繋がれることで、意味をあらわす……未知の意味への期待……。 その蠱惑的な相手が国立図書館の荘重な玄関口へ立ち、艶やかな訪問着姿の色香をあたりに撒き散らしている風情は、 その場の雰囲気にはまったくの不釣合いな感じがあり、行き交う男女もことさらに無関心でいるようであったが、 待ち合わせの相手をすぐに発見できたことであったのは確かだった。 「突然にお呼び立てして、ごめんなさい…… あなたに是非ともご覧になって頂きたいものがあって……」 そのように言われたとき、 小夜子は、思わず、相手が手にしている紫陽花をあしらった大きな縮緬の袋を見つめていた。 それに気づいた坂田由利子は、謎めいた微笑みを浮かべながら答えるのだった。 「いいえ、この中身ではございませんわ…… ご覧になって頂きたいのは、こちらの図書館に蔵書として保管されている一冊ですわ…… それに……この袋の中身……見るものではございません…… むしろ、まとうものであると言った方がよろしいかも…… いずれ、おわかりになりますわ……では、行きましょう」 そうして案内されたのは、館内の奥へ進んだ、 <生物科学・一般生物学>の蔵書が保管されている場所であった。 「分類コード460の468、生態学…… 館内でもこうした奥まった場所にあって、この内容になると、どうやら人影もまばらのようですわね……」 と言うよりは、人影はふたりのほかにまったくなかった。 それは、置かれていた蔵書の内容のせいばかりではなく、その時間帯が閉館間際であったことも関係していた。 実際、閉館が予告されるアナウンスが場内へ鳴り響いた後は、 ふたりは、互いの息遣いさえ聞いて取れるくらいの静寂のなかにあった。 じっと見つめ合ったままでいるふたりの女だった。 小夜子は、恐ろしく自分と顔立ちが似ている相手を前にして、 吸い込まれていきそうな奥深さを意識させられていたが、年齢は相手の方が遥かに上であるとは感じていた、 似ていても相違するのは、年齢ばかりではない、人格そのものはまるで違うのだ、そう思いたいことだった。 「小夜子さんにご覧になって頂きたいというのは…… 実は、私の父が遺した著作ですの…… 父が記述しようと念願しながら、学徒動員で徴集され、戦地で亡くなったために果たせなかった著作です……」 由利子は、黒眼がちの陰翳の深いまなざしで、じっと小夜子を見据えながら、そのように言った。 そして、眼の前の書架から薄っぺらな一冊の書籍を抜き出すと、差し出した。 小夜子には、それを素直に受け取るにも、 語られていることの辻褄の合わないことに戸惑わされて、立ち尽くすばかりのことであった。 記述しようと念願して果たせなかった著作がどうしてあり得るのか。 だが、眼の前にさせられた、古ぼけた茶色の表紙に表題の箔押しの消えかかっている書籍は、 <人類の生態学 坂田久光 著>と読むことができた。 「ここで、小夜子さんに全文を読んで頂く時間は、残念ながら、ありませんわね…… あなたに関係する重要な箇所は、この部分ですから…… ここだけは、しっかりと読んでください……」 由利子は、そう言って、ほっそりとした白い指先でページを括ると、当該の箇所を指し示した。 それを見せられた小夜子は、両眼を大きく見開いて、蒼白の表情に変わっていた。 「……由利子さん、どうしてこのようなことをなさるのですか…… 私には、わけがわかりません……」 小夜子は、初めて疑問で答えたのだった。 相手は、美しい顔立ちに微かな笑みを漂わせて、首を横に振って見せた。 「だめですわ…… 小夜子さんは、私に問い掛ける立場にはないのです…… あなたは、私に言われるがままのことを行えばよいのです…… それがあなたの真実を理解できることなのです…… あなたが権田孫兵衛という老人に導かれて歩いていると思っている<色の道>とやらが…… ただの迷妄にすぎないということをです! さあ、読みなさい!」 顔立ちの優雅さは変わらなかったが、最後の言葉は、威圧のある命令口調となっていた。 だが、小夜子には、できなかった、あふれ出す思いは、その場から逃げ出したい思いでしかなかった。 眼の前にさせられている、文字の一切書かれていない白紙のページを記述として、 読むということはできないことだった。 書かれていないことは読めません……どうして、そのように言い返せないのか、不思議だった。 読むことのできない文字を読むようなことをしてしまったら…… 相手の言いなりに行ってしまったら…… もはや、相手を主人とするような隷属者になるほかない、という脅迫の感じられることだった。 <白紙にある記述>という現実は、 みずからの想像力の無力さをさらけ出させられることでしかなかったのだ。 どうして、誘われるままに、図書館へ来てしまったのだろう…… 悔やんでも悔やみ切れない思いが激しく込み上げていた。 じっとなったまま、顔立ちを引きつらせて立ち尽くしているばかりの小夜子に、 由利子は、皮肉な笑みを浮かべながら、優しく言葉を掛けるのだった。 「わかりましたわ、小夜子さん、では、私が読んで差し上げます…… 亡き私の父が書き記した真剣な事柄です、よくお聞きになってくださいね―― 坂田由利子が語った坂田久光の『人類の生態学』の抜粋 人類の生態という根源的な問いに答えるのは、そう困難なことではない。 答えは少しも困難ではないが、それが明らかとなることに多大な困難が待ち受けていることである。 何故なら、人類の生態は不変であるにも関わらず、 その生態から展開される事柄を<人類の進化>であると呼ぶべきを<生態>そのものが<進化>するとしているからである。 確かに、地球が誕生し、そこに海ができ、その海のなかに単細胞の微生物が生じ、それが魚となり、 魚が陸地へ上がって両棲類となり、両棲類が哺乳類となり、類人猿となり、人間という人類となった。 このいきさつは、これからも詳細に研究されて、人間という人類の誕生経過は、将来、より明確なものとなるであろう。 この過程を<進化>ということであれば、 現在の人間という人類は、いずれは、さらに<別のもの>へと成り変ろうとするということになる、と考えられる。 だが、果たしてそうであろうか。 現在ある人間という人類が最終のものであって、人類は、この最終のものを可能な限り引き延ばすことを行うだけであって、 その先へは、<進化>できないということではないのだろうか。 そのような遥かな未来のことなど、最終的には、神以外にはわかり得ないことだ、このように反駁されることかもしれない。 人知の及ばない領域は、すべて神が補填するというのであれば、 科学と呼ばれていることも、所詮は、人間が概念的に思考するひとつの方法に過ぎないことでしかない。 そう、人間は、概念的に思考する動物である、ここに、人類の生態のありようを解く鍵があるのだ。 人間という人類の生態を成立させている事柄は、四つある、いや、四つしかない。 食欲、知欲、性欲、殺戮欲、この四つである。 食欲とは、その誕生から死に至るまで、物質としての肉体が維持されるために摂取する欲求である。 知欲とは、物質としての肉体が維持される上で、知ることの必要を満たすために考え出す欲求である。 性欲とは、物質としての肉体が人類種として保存されるために、生殖を行う欲求である。 殺戮欲とは、物質としての肉体が維持されるために、他者を殺傷する欲求である。 人類の生態というのは、この四つが成立させていることでしかないということでは、不変の事柄としてあるが、 例えば、食欲は、その摂取可能な対象物を植物から動物に至る雑食として行うことであったり、 性欲は、他の動物一般が一定の周期性を持って同種と行うことを、随意に、しかも異種とさえ行うことであったり、 殺戮欲は、他者に向けられるばかりでなく、自己に対しても向けられものであったりするということでは、 知欲が知ることの必要を満たすことから考え出されるありようには、 物質としての肉体として可能なことであれば、どのようなことも成し遂げようとする野放図がある。 この野放図が生じるわけは、これら四つの欲求が各々に独立したありようを持った欲求であり、 各自の欲求は、各々に対して統御できる力を持っていないということにある。 そして、人間の生態は、そのありようを知欲を通してしか認識することができないという点では、 あたかも、知欲は、他の三つの欲求よりも優位にあるものであり、 そのような知欲を所有する人間は、この地球上において、最も優秀な種であるという誤謬さえ生んでいることである。 何故、誤謬であるかと言えば、その知欲は、みずからの食欲、性欲、殺戮欲を統御できない脆弱な力を示すばかりでなく、 食欲、性欲、殺戮欲があらわす快感においては、それを助長する考えを生み出しさえする欲求であるからだ。 言い換えると、知欲は、人類種が人間として成し遂げてきた文明だとか文化と称するものを、 現在成し遂げた程度にしか行わせなかったものであるということだ。 人類の成し遂げた偉大な文明・文化の遺産、それを大層がる程度にしか、知欲は能力がないということだ。 能力の低い知欲を所有する人類種を地球上の最高位だなどと見なしているとしたら、まったくの誤謬だと言うのである。 例えば、人類の成し遂げた偉大な文明・文化の創造の対極にある、 人類種が行う破壊という戦争の存在を見れば明らかである。 その殺戮欲の公然としたあらわれは、どのような大義名分や美辞麗句で語られようとも、 或いは、愛だとか、憐憫だとか、同情だとかの人間らしさの感動と称されるもので悲惨として語られようとも、 人間が人類の生態として始めた四つの欲求において、 知欲は、殺戮欲を消滅させることはできないということを証明しているに過ぎないのである。 いや、殺戮欲の存在を肯定しているのであればともかく、否定し続ける限りはそうである。 戦争には、反対も賛成もないのである、物を食するのと同様に、他者を殺傷するということがあるに過ぎない。 殺戮欲なくしては、他の動植物を殺傷して、美味なものとして食するということはあり得ないことになるからである。 殺人は、豚や牛や馬や鶏を屠殺することと同じなのだ。 人類における戦争というものは、必要不可欠なものでしかないということである。 戦争を契機として、文明生活に役立つ道具がどれだけ生み出されてきたことか、その事実が物語るのである。 従って、人間における戦争は、どのような最終兵器と称される破壊力のあるものがあらわれようとも、 人類種が絶滅する戦争にまでは決して至らないものとしてあるということも、不変なのである。 殺戮欲は、ひとつの欲求であり、それが生態におけるすべてではないように、 知欲はひとつの欲求であり、食欲はひとつの欲求であり,性欲はひとつの欲求に過ぎないものであるのだ。 その各々は、各自が独立した欲求のありようにおいて、全体性として人類の生態を形成しているのである。 人間が人類種を絶滅に至るまで殺戮するという考えを考えることはできても、 それは、せいぜい、実際には、ひとつの民族を消滅させるようなことでしかあり得ない。 人間が人類の保存維持のために、資源確保として他の種を絶滅に追い込んでいくのと同じ程度のことである。 人類の生態によっては、人類種は、絶滅の危機をできるだけ回避して、保存維持されていくのである。 この事実のなかでは、保存維持されて残るのが優秀な民族、選ばれた民族であるという考えも生まれるだろう。 選ばれた民族には、約束された将来が待っているという教えも生まれるだろう。 だが、この四つの欲求という始まりが人間であれば、終わりも人間であるということでは、 優秀で選ばれた民族こそが生き残るということもない。 人類の生態から展開される、文明とか文化とか呼ばれる一切は、 生まれたときに全裸である赤子が成長と共に身にまとわされる衣服のようなものでしかないからである。 それは、各々の時代における、知欲から生み出される思想の流行を顕著とさせるだけのものであって、 それこそが真実であるとか、或いは、それこそが真理であるとされても、 その時代の流行における真実や真理があらわされていることに過ぎないのである。 何故ならば、知欲は、それよりもさらに真実であること・真理であることを求めているものである。 人類の生態における四つの欲求は野放図であるということが活動力なのである。 この活動力は、野放図な転変流動を繰り返すということでは、それらの欲求に最終というものは存在しないのだ。 ただ、人間が知欲で考え出してきた<箍(たが)>を掛けることしかない。 宗教、倫理、政治、経済、法律といった<箍>である。 それらは、人間が野放図を囲い込むために作り出した<箍>であるから、知欲の欲求に応じているものである。 <箍>を具体的にあらわそうとすれば、それは、その概念的思考にあることを言語化しなければならない。 従って、宗教、倫理、政治、経済、法律といった<箍>は、 概念的思考の<箍>であり、言語という<箍>であるということになる。 野放図が野放図であり、それにどのような<箍>を掛けるかということが人類史であれば、 <箍>は、最初に考え出されたものよりも、順次複雑なものとなっていく過程を成行きとせざるを得ない。 何故なら、最初の<箍>は野放図を囲い込むために未熟で不充分なものであったと考えられ、 次にさらに複雑な<箍>を考え出して野放図を囲い込むことをするが、 それもやはり未熟で不充分なものであると考えられ、それを繰り返す過程を進行していくからである。 従って、縄文時代の<箍>よりも室町時代の<箍>の方が複雑化しているのは事実であるが、 ここに、また、ひとつの誤謬が生まれる、それは、複雑化は進化をあらわしているとすることである。 または、複雑化は、単純でないことから、深化を意味しているとすることである。 これは、誤謬である。 人類の生態は、食欲、知欲、性欲、殺戮欲という四つの欲求から形成されている全体性であって、 それは、各々が独立した機能の欲求の全体性であることから、相互には、相反と矛盾を持ったものとしてさえある。 この相反と矛盾がひとつになる統合はあり得ない、それを果たさせる力が人間のなかにはない。 従って、人間が将来<別のもの>となる進化は決して果たし得ないことなのである。 現在ある人間が最終のものとしてあるということだ。 これまでと同様、物質としての肉体を微細な点に至るまで、探求するという試みが続けられるであろう。 しかし、遺伝子の仕組みがどうであろうと、脳の働きがどのようであろうと、 解明されたと思われた時点では、未だに不明な事柄が存在するということがわかるだけである。 人類の野放図は、認識し得たと思えたほど、不明というものを作り出すだけのことである。 これは、探求ということが深化をあらわしているように見えるが、 不明の壁は探求の一歩から変わらないものとしてあるのだから、 続けられる深化の探求が真理を導くということは、最終を意味するということは決してないために、深さがあり得ないのである。 先に述べたように、このように、人類の生態という根源的な問いに答えるのは、そう困難なことではない。 答えは少しも困難ではないが、それが明らかとなることに多大な困難が待ち受けていることである。 ただの歩行の時代よりも荷馬車の時代、それよりも、船舶の時代、さらには、自動車の時代、そして、飛行機の時代、 人類が宇宙へ進出していくのも時間の問題であろう、それは果たされるはずである。 すべての人間は、現在よりも、より善く成りたいと思っている、 だから、人間はそのように進化するものであると考えたいのである。 にもかかわらず、人類の知欲による複雑化の過程が人間を<別のもの>へと成り変ろうとさせる進化ではないとすることや、 知欲の探求には深化さえあり得ないなどとすることは、この希望を根底から打ち消す発言をしていることにほかならない。 血迷っているか、気違いか、阿呆か、無能か、そのような者の発言であるとしか見なされない。 だが、事実である以上、仕方がない。 現在ある人類の生態は進化しない、人類の生態の全体性は、知欲ひとつの欲求では変えることができない、 という人類の最終過程を我々は生き続けていることでしかないということは。 ――如何かしら、小夜子さん、おわかりになって…… <縛って繋ぐ力による色の道>が導く<民族の予定調和>など、起り得ないことの概念的思考の迷妄であって、 あなたがそれに追従しているのは、 ただ、それが官能を高ぶらされる性的恍惚を知覚させてくれることだからではないのかしら…… 人間が高ぶらされる性の快感を得ようとすることであれば、 サディズムであろうが、マゾヒズムであろうが、フェティシズムであろうが、カニバリズムであろうが、一緒のこと。 そのような複雑多様化している性の概念を思考するのは現代の流行であって、 いずれは、もっと複雑なありようが人間にはある、という学説があらわれることになるだけのことです。 複雑多様に思考するというのは、知欲の定められた活動だからです。 それでなければ、各種のエネルギーを利用して、多様な道具を生み出して、複雑に構造化されていく文化生活、 あなたは、現在、それを享受できないのではありませんか。 しかし、外観はどのように見事な衣装をまとっていても、生まれたままの全裸をさらけ出されれば、 実際は、猿という動物から人間に移行するときに行なわれた、 革新的な変化として脳にある<永遠の黄昏>があるだけということになるのです…… 権田孫兵衛という方も、人間が四つの欲求を所有しているくらいのことは、ご存知のはずですわ。 しかし、その四つの欲求が人類の生態として、 未来において決定的に変化を生じさせないものとしてあるということを理解なさっておられないというだけです。 ですから、<民族の予定調和>などという具にもつかないことをおっしゃられるのです…… まあ、エンターテインメントとしては、少々の興があることかもしれませんけれど…… あら、小夜子さん、納得なされていないご様子ですわね…… いいですわ、証拠をお見せしましょう…… あなたのためになることならば、私は、喜んで協力いたしますわ…… <民族の予定調和>は<縛って繋ぐ力>がそれを成し遂げるのでしょう…… 私があなたに縄を掛けて、それを示して差し上げますわ…… さあ、着ているものをすべてお脱ぎになって……」 優雅な美しい顔立ちは少しも崩さずに、由利子は、鋭いまなざしで相手を見やるのだった。 そして、手にしていた紫陽花をあしらった大きな縮緬の袋を開けると、麻縄の束を取り出したのだった。 小夜子は、申し渡されたことにびっくりしていたが、示された縄にはさらに驚いていた。 その驚きは、由利子のほっそりとした白い手が眼の前へ縄を掲げて見せることで、狼狽へと変わり、 「さあ、早く、全裸になりなさない!」と叱咤されることで、不安と恐れを強迫されるものへと移っていった。 冗談などではないことは、亡き父親の遺言のようにして語られた言葉の真剣さが物語っている。 小夜子は、思わず、後ずさりするようにして、震える声音であらがった。 「いや、いやっ、裸になるなんて! このようなところで裸になるなんて、嫌です!」 由利子は、美しい顔立ちに謎めいた微笑を浮かべながら、優しく答えていた。 「何をおっしゃいますの、あなたは、<民族の予定調和>の表象としての女性ですよ。 縄を見せられて全裸を晒すことができないなんて、そのようなこと、できないわけがないじゃありませんか。 いや、むしろ……私から、いつ縄を示されるか、それをずっと待ち望んでいたことではないのかしら…… あなたは、最初にお会いしたときから、私のことを魅力的な女性だと感じていますものね……」 小夜子は、なよやかな両肩を震わせるようにして、つぶやくような言葉を吐いていた。 「嘘、嘘です、そんなこと…… 私があなたから縛られることを望んでいたなんて……」 由利子は、小夜子の方へさらに一歩近づくと、麻縄を床へそっと置いた。 それから、相手の身に着けているスーツの上着を脱がせ、ブラウスのボタンを外し始めるのだった。 図書館の閉館時間はとっくに過ぎていた。 ふたりの女は、その場所に孤立させられたように、静寂のなかにたたずんでいた。 ただ、ひとりの女がもうひとりの女の衣類を脱がせていく、衣擦れの音だけが室内にこだまするだけだった。 小夜子は、大人しく、されるがままだったのだ。 どうして、相手にされるがままになってしまうのか、不思議でならないほど、自然な振舞いの感じがあったのだ。 ブラウスを脱がされ、ブラジャーを取り去らされ、スカートを下ろされ、ショーツへ相手の指先が掛けられても、 まるで、みずからの手で脱衣しているような自然な感じで、生まれたままの姿になっていくことができたのだった。 「艶めかしい姿態ですわね…… 女らしい優美で悩ましい曲線が雪白の光沢を放つしっとりとした柔肌を包んで…… 男性であったら、思わず、ものにしたいと感ずる蠱惑的な色香が匂い立つように……」 身に着けていた衣類をすべて脱がせ終わった女は、一歩下がって、 しげしげとしたまなざしを相手へ投げかけて言うのだった。 小夜子は、紅潮した頬の顔立ちを背けるように俯かせ、 双方の手で乳房と下腹部を覆い隠す恥じらいを示していた。 しかし、その両手も由利子に華奢な手首を取られて、 難なく覆い隠されているものをあらわとさせていくのだった。 「ふっくらと瑞々しい綺麗なかたちの乳房…… つんと立ち上がった桃色の乳首は芳しさを漂わせる果実のような愛らしさをのぞかせて…… 下腹部にある女らしい優しい盛り上がりを見せる小さな丘の神秘的な深い亀裂を…… 夢幻的とも映る柔和な漆黒の靄に隠すという麗しさをかもしだしている…… 女は、そこに、その顔立ちの美しさに負けず劣らずの美麗な姿態をあらわとさせているのだった…… とでも、男性だったら記述するのかしら、何ともありきたりな表現の感じがしないでもないですけれど…… それでも、女の美しい姿態に縄の緊縛が映えるということは、否定できないことのようですわね……」 由利子は、微笑みを漂わせた顔立ちを小夜子の方へ向けると、床から拾い上げた麻縄を掲げて示すのだった。 小夜子は、俯かせていた顔立ちから、盗み見るようなまなざしでその縄を見つめていた。 その大きく見開かれた瞳には、驚きと戸惑いと不安と羞恥とが入り混じった思いがあらわされていたが、 さらに、付け加えられていく思いは、みずから、ほっそりとした白い両腕をそろそろと背後へまわし、 華奢な両手首を重ね合わせる仕草を取らせるものであったのだ。 「……そうですわね、縄を見せられれば、縛られることを望む、本当に良く躾られていますこと…… 権田孫兵衛という方も、この点にかけては、実際的な思想家であるのかもしれませんわね……」 生まれたままの全裸の姿にある女の背後へまわった由利子は、 従順に重ね合わされた両手首へ、ふた筋とした麻縄を巻き付けながら喋り続けるのだった。 「小夜子さんは、こうして、何度も何度も多様な縄掛けを受けながら、一度でも考えたこと、お有りになる? あなたが全裸の姿を縄で緊縛されることが、実は、大変に重要な事柄をあらわしているということを……」 がっちりとした後ろ手に縛り上げられていく小夜子は、 みずからの肉体が置かれた状況の伝えてくる感触に寡黙になっていくばかりで、 相手の言葉さえ耳に入ってこない様子だった。 「縄の緊縛による拘束感は、否応なく自己へ閉じこもらせるほど、 小夜子さんにはしっくりといくことのようですわね…… あなたは、文明や文化という衣装を脱ぎ去って、四つの欲求があからさまとなる全裸の姿態にあって、 縄掛けされるという<縛って繋ぐ力>に満たされる、その高ぶらされる官能の思いにあって、 想像力は<民族の予定調和>へと飛翔していく……権田孫兵衛さんなら、このように言われることなのかしら…… 詩的な幻想……悪くはないですわ…… 性的官能にまつわる事柄を詩的な幻想に置き換えると、下世話な感じは希薄なものになりますものね…… 行っていることは同じであっても、概念的思考が組み合わせる言語の如何によって…… 陰茎が膣へ挿入されて抜き差しされ、あふれ出す女の粘液に勢いづかせられて、男は精液を放出する…… このようなことも…… 深い淵から滴り落ちる女の神と男の神のものがまざりあって島を生んだ、と言えますものね…… 同一の事柄でも、相似は言うに及ばず、相反でさえ表現できる、概念的思考による言語ならではものですわね…… 自然の植物繊維から撚られた縄で緊縛する縄掛けも一緒のことです…… 私がこうして後ろ手に縛る、それから、さらに、残りの縄を前へまわして胸縄を掛ける…… あなたにあっては、官能を高ぶらされて<色の道>を歩む想像力かもしれませんけれど、 人類の生態学からすれば、この緊縛の形態というのは、 現在の縄掛けよりも、過去にあった仕方の方が単純であった、という事実が示されていることですの……」 由利子の縄は、小夜子のふっくらとした美しい隆起を見せるふたつの乳房の上部へ掛けられ、 幾重にも巻き付けられて背後で縄留めされた、すぐに、二本目の縄が背後へ結ばれて、今度は、 下部へ掛けられて幾重にも巻き付けられ、緩みの起きないように、両脇の背後から締められて縄留めされていったが、 その縄掛けは手際の良いものだっただけに、小夜子は、肉体の置かれる状況へどんどん追い込まれていくのであった。 「縄による全裸の女体緊縛において、人類の複雑化の過程を見ることができるということですわね…… では、どうして、縄掛けは複雑な形態へと向かわなければならないのでしょう…… 縄による全裸の女体緊縛など、異常性欲者の自慰行為である、 と見なしているような性科学では、答えの出ることではありませんわね。 知欲の欲求に従った複雑化の過程を分類していくだけで答えが出るという方法を科学的としているなら、 科学的な概念的思考は、さらに複雑化することを求められているというだけです……」 三本目のふた筋とされた縄が背後へ結ばれ、小夜子のほっそりとした首筋を左右から割って前へと下ろされ、 胸縄へ絡められて締め上げられていくと、立ち上がっていたふたつの可憐な乳首はつんとした愛らしさを増すのであった。 その縄の残りが優美な腰付きのくびれを際立たせられるように巻き付けられていくと、 被縛の女は、柔らかに波打つ黒髪を震わせながら、ああっ、とやるせなさそうな声音をもらすのだった。 「生まれたままの全裸にされ、縄で緊縛されただけで、性的官能を高ぶらされてしまう素直な女…… 小夜子さんが<民族の女性>であると男性からもてはやされ、その気になっていることだとしても、 仕方のないことかもしれませんわね、あなたは、とても魅力的ですもの…… けれど、いま、この縄を掛けているのは、坂田由利子です。 これから、あなたを喜びの極みにまで昇りつめさせるのも、私であることを承知しておいてくださいね。 さあ、そのしなやかで美しい両脚を大きく開きなさい!」 最後の言葉には、有無を言わせない超然とした威圧が感じられた。 小夜子は、美しい顔立ちにおどおどとした表情を浮かべながら、 言われるがままに、そろそろと両脚を開いていくのだった。 相手に掛けられた縄で官能を高ぶらされ、言いなりになっていくことで、高ぶらされる官能を昇りつめる…… それは、甘美に疼かせる期待を意識させるものであったが、同時に、恐ろしさを込み上げさせてくるものでもあった。 小夜子は、成行きのままに、ここまで来てしまったことに初めて恐れを抱いていた。 <縛って繋ぐ力による色の道>の<信奉者>による縄掛けでない緊縛によって官能を高ぶらされていること…… 明らかに邪道とされる行為であった…… その邪道の官能が導く先に待っている得体の知れない薄闇…… それを意識させられて戦慄するのだった。 「さあ、もっと大きく両脚を開くのです!」 坂田由利子の言葉は、叱咤していた。 「由利子さん、許してください! このようなこと、もうやめにしてください! 私には、できません! 恐ろしいのです、あなたの言うがままに惹き込まれていってしまうのが、恐ろしいのです! お願いです!」 小夜子は、突然、泣き出さんばかりの形相で、相手へ訴えかけていた。 「申し上げましたでしょう、小夜子さんは、私に問い掛ける立場にはないのです。 あなたは、私に言われるがままのことを行えばよいのです。 さあ、その美しい両脚をもっと開いて、あなたの蠱惑的な女の割れめをさらけ出しなさい!」 小夜子は、どうにも仕方がないというように両眼をつぶると、 緊縛された裸身をすくませるように身悶えさせながら、さらに両脚を開いていくのだった。 下腹部にある女らしい優しい盛り上がりを見せる小さな丘の神秘的な深い亀裂は、 夢幻的とも映る柔和な漆黒の靄から麗しく顔をのぞかせていた。 由利子は、手にしていた書籍の<人類の生態学 坂田久光 著>と箔押しされた背表紙をその亀裂へ押し付け、 下から突き上げるような力を加えた。 「ああっ」 小夜子は、思わず、のけぞるような身悶えを示したが、 「さあ、あなたの柔らかで艶めかしい太腿で挟み込んで、昇りつめなさい。 昇りつめるまで、咥えた書籍を離すことは許しませんからね。 落したら、行くまで繰り返されるだけです」 と由利子は言うなり、相手から素っ気なく離れていくのだった。 「ああっ、そ、そんな! 私は、いやです! このような……このような由利子さんのお父様を冒涜するような振舞いは嫌です! お願いです、お願いです、許してください、許して!」 小夜子は、桜色に上気させた美しい顔立ちを悲痛に歪めながら、涙声になっていた。 だが、女の意地は、悩ましい女の亀裂を割って股間へ挟み込まされた書籍をしっかりと咥えたまま、 落下させることはしないという振舞いを示しているのだった。 「冒涜ですって! 何をおっしゃられるの、小夜子さん。 あなたに私の父を冒涜できるほどのありようがお有りになって! 記述されていない言語概念を想像力を持って読みあらわすこともできないあなたが! あなたが歩み続けているという<色の道>は、 <人間の抱く想像力こそが人間本来のものとしての神であるというヴィジョンを実現すること>とされる、 <民族の予定調和>というものなのでしょう。 それでしたら、あなたの想像力は、そうあるべきではないのですか。 貧困な想像力しか持たないあなたに、私の父を冒涜する力などないということですよ。 いま、あなたが女の割れめに咥え込んでいるのは、ただの書籍にすぎないのではありませんか。 いや、そのなかに記述されている何たるかを理解し得ない者に、それは、ただの書籍でさえないのかもしれません。 あなたの官能を高ぶらさせる道具としてあることが有効利用と言える物質にすぎない、張形と一緒と言うことです。 冒涜……それは、形骸化した権威を維持させるときだけに使われる、尊厳のお体裁ということではないのかしら。 あなたは、権田孫兵衛老人の尊厳のある縄掛けと私の縄掛け、どれだけの相違が感じられますか。 いや、どれだけの性感の高まりという相似を感じられますか。 言葉にして答えられないと言うのなら、 あなたが手ほどきされた<色の道>というものがどれほどのものか、 その美しい肉体であらわして見せてください!」 艶やかな訪問着姿の由利子は、素っ裸に厳しい縄を掛けられている女を前にして、 優雅な色香をあたりに撒き散らしている風情さえあるのだった。 生まれたままの全裸を後ろ手に縛られ、胸縄を施され、その上に、 股間へ挟まされた書籍で敏感な女の箇所へ刺激を受けて官能を高ぶらせる、 喜びへと昇りつめられなければ、やり遂げるまで続けさせられる…… まるで、女衒から<色の道>を仕込まれている女郎と言えば、古色蒼然とした喩えということになるだろうか。 小夜子は、悔しさで胸が張り裂けそうになっていたが、その胸には、 厳しい麻縄が上下から掛けられて、乳房を突き出すようにさせられてはいても、破れ出すには至らないことだった。 悔しさは、相手の顔立ちが恐ろしく自分と似ているということで、 いや増しに掻き立てられるものでしかなかったが、避けられない相手であるとも思わされていたのであった。 屹立する書架に挟まれた通路で行われていたことであったとしても、 館内を見まわる警備員がいつあらわれるかわからない。 このようなありさまを人様に見られでもしたら、憲法第一七五条、公然猥褻物陳列である。 たとえ、図書館の書籍の陳列のそばにあったことだとしても、 人間は書籍に書かれた言語を理解し得る動物であるかもしれないが、 書籍の言語そのものではないことは事実だった。 しかし、由利子は、そのような懸念などまったく感知しないというように、 落ち着いた優雅な物腰で成行きを眺めているだけだった。 小夜子には、もう、どうしてよいのかわからない、という思いがあふれ出していた。 すると、太腿が我知らずに弛緩して、汗に濡れ始めた書籍を下へ滑らせるのだった。 それを知ると、由利子は、書籍の背表紙が女の割れめへ食い込むように、挟み込ませるのだった。 小夜子は、そうされることがたまらなく惨めなことに思えた。 だが、挟まされた書籍の背表紙が割れめにある敏感な小突起や、花びらばかりか果肉にまで及んでいても、 それだけの圧迫されるような刺激では、高ぶっていた官能ではあったにせよ、それ以上にはならないのだった。 むしろ、挟み込んだ書籍を落すまいと懸命になることは、官能を鎮めさせていくものであった。 優美な腰付きからしなやかに伸びた両脚を悩ましくうねらせ、くねらせしても、 書籍から与えられる刺激は知れたものだった。 時間は刻々と過ぎていったが、全身から滴らせる汗の量は増しても、 割れめからあふれ出させる女の花蜜は知れたものだったのだ。 小夜子は、うん、うん、うん、と唸りながら、みずからを高ぶらせることに懸命になっていたが、 <人類の生態学 坂田久光 著>を股間から滑り落させるだけのことでしかなかったのだった。 「由利子さん、お願いです、許してください、私が思い上がっていました…… ごめんなさい……できません、やり遂げられません……許してください、お願いです!」 小夜子は、ついに、泣きじゃくりながら哀願しているのだった。 「できないはずのないことですわ…… あなたには、まだ、修行が足りないというだけのことではないかしら…… あなたは、想像力をまるで使っていないようですものね…… もっとも、そのような貧困な想像力など使わなくても、 喜びを昇りつめるということは、それほど難しいことではないのではなくて……」 由利子は、優雅な美しい顔立ちに微笑みを浮かべて、小夜子の方へ近づいてきた。 そして、掛けられた胸縄でせり上げられた華奢な両肩へ優しく双方の手を置くと、 泣きじゃくって俯き加減になっている小夜子の顔立ちへ、みずからの顔立ちを近づけていくのだった。 びっくりしたのは小夜子だったが、そのときは、もう、緊縛の女の綺麗な唇は、 艶やかな訪問着の女の美しい唇で塞がれているのだった。 「む、む、む、む、む……」 小夜子は、それが待ち望んでいたことでもあるかのように、自然と唇が半開きとなっていた。 とろけるように柔らかで甘美な舌先がもぐり込んできたが、それが口中を優しく強くうごめきまわって、 やがて、思いを込めたようにみずからの舌先へ絡まってくるのをされるがままに受けとめていた。 鎮められたかに思えた官能は、一気に燃え立たせられ、 そのまま続けられることを望ませる強い快感の疼きがそこにあった。 ぬめりをおびた舌先と舌先が絡まり合って、息の詰まらせられるような胸の高鳴りが緊縛の胸を震わせていた。 「女同士でこのようなことをするの…… 小夜子さんは、お嫌かもしれませんわね……」 突然、唇を離した由利子は、深い陰翳のあるまなざしでじっと相手を見つめながら、言うのだった。 小夜子は、行為中止を唖然とさせられると同時に、そのとき、超然とした威圧感がありながら、 しっとりとした穏やかで落ち着いた相手の優雅な顔立ちを初めて美しいと感じていた。 全裸を縄で緊縛された女は、その縄掛けを行った相手に対して、 柔らかに波打つ黒髪を揺らせながら、否とはっきりと首を振って見せた、 それから、綺麗な形をした柔らかな唇を半開きにさせて、 相手から与えられる快さを喘ぎ求めるように、その顔立ちを突き出すようにさせていった。 由利子の同じ形をした美しい唇が優しく重ね合わされてきた、 そして、半開きさせた口へ相手の侵入を誘い入れるように、軽く吸い上げてくるのだった。 恐る恐るのぞかせた舌先は、強く吸い上げられることで口中へ取り込まれ、 甘くねっとりとした感触の舌先で、転がされ、撫でられ、絡められを繰り返され、 口の端から唾液のしずくが流れ出すまで続けられていったが、 その頃には、全裸でいる女にも、置かれている肉体の状況が効果を発揮し出していた―― 生まれたままの裸姿にあること、それは無防備であることを明確に自覚させる、 防備する両手を縄で後ろ手に縛られれば、みずからを防備するものは、もはや羞恥しかない、 その羞恥も、後ろ手に縛られた縄がふたつの乳房を上下から挟むようにされた胸縄を加えられ、 首筋からの縦縄によって絡められた胸縄が突き出すような乳房の格好にまでさせられると、屈辱の色合いをおびてくる、 みずからの思いをよそに、ふたつの乳首は欲情をあらわすようにつんと立ち上がって、 しかも、みずからの思いは、防備を一層奪われたなかで、されるがままになるという隷属を強いられる、 その隷属の思いは、身体の随所から柔肌を圧迫してくる縄の緊縛感が当初の冷たさから温かさに変わり、 やがて、熱さを意識させるようになってくると、縄で縛られている抱擁感さえ思わさせるようになる、 みずからへ縄掛けした相手が熱く抱きしめているという思いになっていくことだとしたら、 無防備なみずからは、相手に隷属して、されるがままになるほかなく、 されるがままになるということは、官能に火をつけられ、掻き立てられ、煽り立てられ、燃え上がらせられる、 そして、喜びの頂点を極めるということへの期待が生まれたことをあらわすほかないものとなる、 つまり、性的官能は、火をつけられれば、行き着くところへ行かなければ収まらない、という属性の故であり、 しかも、性的官能は、常時は働いているものであるから、発火さえ与えられれば成り立つ、ということである、 全裸にした女性を縄で緊縛することが陵辱を行うための手段にしか過ぎない場合は、 このような悠長な過程は起らないから、縄による緊縛は、陵辱を意味するだけのもにしかならない、 喜びの頂点への期待を抱く思いに至らない被縛者は、ただ、暴力と恥辱を受けているとしか感じられない、 この暴力と恥辱の表現がサディズム・マゾヒズムと称されるものであるから、 暴力と恥辱を表現するために、肉体へ加えられる行為は、苦痛を伴った殺傷から殺戮に至るまでのことになる、 火をつけられれば、行き着くところへ行かなければ収まらない性的官能は、苦痛に喜びを求めることになる、 苦痛そのものが喜ばしいものとしてあるからではなく、その苦痛を通さなければ喜びの頂点へ到達できないために、 苦痛を喜びと倒錯するということである、 しかも、その殺傷から殺戮に至るまでの苦痛に意味が見出せるとしたら、その苦痛は至福とさえあらわされる、 苦痛は、死をも乗り越える性的法悦とそれからの復活さえ意味するようなものとしてあれば、有意義となる、 裸身を皮膚が裂けるまで鞭打たれ、腰の骨が砕けるような重い十字架を担がされ、両手両足を貫く釘を打ち込まれて、 暴力と恥辱の見せしめとして、死に至るまで磔にされたありようが人類の救済を意味するという有意義である、 整合性のある存在理由を求めようとする方法が科学である立場とすれば、そこに、無意味ということはあり得ない、 概念的思考の整合性は、意味を取り結ぶために行われるものであるからだ、 人間のあらわす殺戮欲の表現を意味として捉えるには、歴史過程として、サディズム・マゾヒズムの定義が必要であった、 サディズム・マゾヒズムは、人類にある殺戮欲の存在を明確なものとはさせたが、 人間の探求としては、もはや、せいぜいエンターテインメントの表現として用いられることで残存するようなものであろう、 苦痛を喜びと倒錯するというありようは、性的官能の問題と言うよりは、遥かに心理学の問題である、 性心理学というありようが性的官能の問題と心理学の問題をただ混交させているだけというようなものだとしたら、 因習の問題を文明化の遅れている民族の悪習のあらわれとだけ見なすようなことと相似である―― 似たように美しい全裸の小夜子と着物姿の由利子が、 国立図書館の<生物科学・一般生物学>の区画、<分類コード460の468、生態学>の前で行っていたことは、 女が女を相手として官能を高め合う性愛の行為としては、レズビアンの愛欲と言えるものに違いなかった。 ふたりが互いをどのように思っていたかは別として、 ふたりが絡み合うことで官能を高ぶらせて、気持ちのよい高みにまで昇ろうとしていたことは確かだった。 小夜子は、みずからを縄で緊縛した相手のされるがままだった。 由利子の口中へもぐり込ませた舌先は、女の芯から突き上げられるような甘美な疼きを煽り立て、 割れめへ挟み込んでいる<人類の生態学 坂田久光 著>を双方の太腿で締め上げさせるような高ぶりを示させていた。 その背表紙には、あふれ出せた女の花蜜が輝きをおびて滴り落ちているのがわかるくらいであったのだ。 由利子には、悩ましく鼻を鳴らすようにして、喘ぎ出した小夜子が身悶えして求めていることが察知できた。 口中で、弱く、強く、激しく、うねり、くねり、こねまわす舌先の妖艶なうごめきに合わせるようにして、 彼女は、割れめへ食い込んでいる書籍を片方の手でつかむと、 その背表紙を弱く、強く、激しく、という具合に、深く食い込ませるように押し上げ始めたのだった。 「うっ、うっ、うっ……」 背表紙の当たる箇所、敏感に立ち上がった愛らしい小突起、果肉をあらわにして開いた花びら、可憐にすぼまった菊門、 これらは、女の割れめがもはや咥え込んだものを離さないという強烈な収縮を示すなかで、さらに鋭敏さを増して、 小夜子の官能を階段を昇っていくような具合に高潮へと運んでいくのであった。 「う〜うっ」 突然、激しいうめき声と共に、縄で緊縛されている小夜子の全裸がびくんと突っ張った。 由利子のつかんでいた書籍もあらん限りの力で相手の股間へ突き上げられていた。 小夜子は、びくっ、びくっ、とした痙攣を悩ましい曲線に縁取られた腰付きから、艶めかしい双方の太腿、 さらには、しなやかな美しい両脚にまであらわして、唇を重ね合わせているのがもどかしいというように離れていき、 床にへたり込まずに立っているのがせめても女の意地とでも言うように、官能を昇りつめた喜びに浸らされていた。 「如何かしら……よかったかしら?」 由利子が相手の股間から優しく書籍を引き抜きながら、愛らしく唇をすぼめて見せながら語り掛けていた。 「ええ……」 小夜子は、恥ずかしいとでも言うように、桜色に紅潮した顔立ちを僅かに俯かせながら答えるのだった。 「そうですわね……小夜子さん…… いま、あなた、とても美しい顔立ちをなさっていらっしゃいますもの…… あなたが<色の道>など歩いていない女性であったら、とつくづく思いますわ…… そうでしたら、私の<超絶生態学>の研究を手伝ってもらえるでしょうに……でも、だめですわね…… あなたは権田孫兵衛老人の信徒ですものね……<民族の予定調和>の表象ですものね…… とても、残念なことです…… でも、私は、あなたをもう一度昇りつめて差し上げることくらいは、できますことよ……」 艶やかな訪問着姿の色香をあたりに撒き散らしている美しい女は、そう言って、 官能の喜びの余韻もまだ醒めやらない、生まれたままの全裸を縄で緊縛された女へまとわりついていくのだった。 小夜子は、狼狽を感じていた。 されるがままに昇りつめさせられた快感は、 邪道の官能が導く先に待っている得体の知れない薄闇といった淫靡なものではなく、 権田孫兵衛老人の尊厳のある縄掛けと由利子の縄掛け、 双方にどれだけの相違が感じられるかという疑問を残したものであったのだ。 いま、由利子の父親が記述したとされる書籍の代わりに、 みずからの股間へ、白くほっそりとした美しい指が二本、おもむろに差し入れられてくるのだった。 小夜子は、一度ならずも二度までも、邪道によって官能の喜びを極めることを考えると、 思わず、艶めかしい太腿を閉じ合わせて、夢幻的とも映る柔和な漆黒の靄に隠されて、 女らしい優しい盛り上がりを見せる小さな丘の神秘的な深い亀裂へ迫る、 相手の侵入を拒む仕草を示すのだった。 しかし、由利子は、そのような態度をまったく意に介さないというように、 ふっくらと盛り上がる漆黒の靄の夢幻を白い指先で優しく梳き上げては、 掻き分けるようにして、女の割れめをあらわとさせていくのだった。 「ああっ、だめっ、由利子さん、だめっ……」 小夜子は、あらがう声音をもらしていたが、そのか細さは、 悶えさせる腰付きのか弱さであり、閉じ合わせていた太腿の脆弱であった。 「ああっ、ああっ……」 由利子のしなやかな二本の指先は、割れめを左右へ押し開いて、 奥へ奥へとぐいぐい差し入れられてくるばかりであったのだ。 すでに、立ち上がってしまっている愛らしく鋭敏な小突起だった、 妖美な花びらを開き切って果肉をさらけ出させている深淵であった、 指先が思いのままにうごめくことができるように、 芳しく匂い立つような女の花蜜は、どろどろにあふれ出して待ち望んでいたのだった。 由利子の指先は、立ち上がった小突起をつまんでは、こねくりまわす、ということを繰り返していたが、 小夜子は、ああっ、だめっ、だめ、行きそう、もう、行きそう、と甘い鼻息をもらしながら、 緊縛された裸身を我慢ができないというようによじったり、ねじったりすることが精一杯の仕草であった。 やがて、二本のしなやかで白い指は三本となり、 妖艶な花びらの奥、その深い淵へ、ねじり込まされるようにしてもぐらされていった。 「ああ〜ん、ああ〜ん」 小夜子のやるせなそうな声音は、切なそうな声音へと変わり、泣き声に近いものとなっていった。 由利子は、心得ていると言うように、 深くもぐらせた三本の指先をうごめかせて、吸引と収縮をじっくりと確かめるようにしてから、 人差し指の第二関節まで入るあたりの膣壁の前方を責め始めるのだった、 そこの粟状に盛り上がっている箇所が、まさぐられるように、掻き出されるように、激しく愛撫されたのだった。 「ああん、ああん、だめっ、だめっ、行ってしまう〜〜」 小夜子は、波打つ艶やかな黒髪を左右へ打ち振るって、 縄で緊縛された裸身をのけぞらせるようにさせながら、大きくびくんとした硬直を示した。 それからは、もう、立っているのがままならないというように、 腰付きから太腿までをぴくぴくと痙攣させながら、床にへたり込んでいくのであったが、 羞恥は太腿を閉じ合わさせて、それを隠させようとしていたのであろうが、 女の割れめから、ぴゅっ、ぴゅっ、と吹き出させている粘液は、きらめくしずくとなって飛び散っているのだった。 小夜子は、すすり上げるように泣きじゃくっていた、 それが阻喪をした羞恥と屈辱からの思いのものであったのか、 泣き声を上げなければならないほどの高ぶらされた官能の快感の極みのものであったのか、 判然としないことだったが、美しい優雅な顔立ちに微笑を浮かべた由利子は、 床へ横座りの姿勢となって必死に身を縮こまらせるようにしている相手を見つめて、 紫陽花をあしらった大きな縮緬の袋から、さらなる麻縄を取り出して見せるのであった。 「如何でした……今度も、よかったかしら?」 優しく問い掛ける由利子の言葉に、小夜子は、顔立ちをかたくなに俯かせたまま、返事をしなかった。 返事をしなくても、縄で縛り上げられた生まれたままの全裸は、 ぴく、ぴく、とした官能の恍惚の余韻を痙攣と火照りであらわしていた、 股間のある床のあたりは、粘液のしずくが溜まってきらいめいていることが明らかとさせていた。 「小夜子さんとは、また、お目にかかる機会もあることかもしれませんが…… <私との離れられない結び付き>を思い出として刻んで頂くために…… もうひとつ縄を掛けても構わないかしら……」 由利子の質問は、答えを求めていない超然とした響きのあるものだった。 小夜子と恐ろしいくらいに似ている顔立ちの女は、相手の裸身を床から起こさせて、跪かせる格好にさせるのだった。 縄で緊縛されている全裸の女は、放心したように茫然となったまま、されるがままでしかなかった。 優美な腰付きのくびれを際立たせている腰縄へ、新たな縄が掛けられていった。 ふた筋とされたその縄は、愛らしい感じの臍のあたりで結ばれて、縦縄として下ろされた。 夢幻的とも映る柔和な漆黒の靄に隠されて、 女らしい優しい盛り上がりを見せる小さな丘の神秘的な深い亀裂まで持ってこられると、 女の割れめが際立つくらいに深々ともぐらされて、 艶めかしい尻の間からたくし上げられると、背後でがっちりとした縄留めがされるのだった。 まだ、甘美な疼きの敏感に残る箇所へ施された股縄であった。 小夜子には、もはや、惨めなくらいに食い込むように施された股縄へ、 見るともなしのまなざしを落すほかに、言葉はなかった。 由利子は、小夜子の阻喪した床のしずくを布切れで綺麗に吹きとっていた。 それから、女の花蜜でぬれそぼった<人類の生態学 坂田久光 著>の書籍を綺麗にすると、 屹立する書架のもとあった場所へ収めるのであった。 「さあ、行きましょう…… 小夜子さんには、お別れに…… ご覧になって頂きたい素晴らしい光景がございますのよ……」 由利子は、そう言うと、小夜子を床から立ち上がらせ、 縛り上げた縄尻を取って引き立てるようにして先へ歩ませるのだった。 長い廊下を幾つも巡って歩かされていったが、茫然となっている小夜子には、 みずからのこと以外は、まったく頭に入らない様子だった。 そうして、たどり着かされた場所は、広々とした閲覧室であったが、人影はなかった。 図書館は閉館し、照明もすでに落されていた、ふたりの女は、いまや、闖入者に過ぎなかった。 だが、そこで、図書館の警備員と出くわしたとしても、 坂田由利子のしっとりとした穏やかで落ち着いた喋り方や振舞いの優雅さ、有無を言わせない超然とした威圧感は、 圧倒される妖美を示す幽霊の存在を思わせるようなものであったかももしれない。 その妖美な幽霊が従えている、縄で緊縛された生まれたままの全裸の女性は、 愛玩物のようにして連れられた白く美しい生き物にしか見えないことだったかもしれなかった。 公共の図書館において、緊縛の全裸女性が徘徊するなど、非現実なことに違いないからである。 その幽霊のような坂田由利子は、小夜子を窓辺へ立たせると、カーテンを引き、窓を大きく開け放った。 図書館の広々とした閲覧室の開かれた窓の向こうには、黄昏が待っていた。 昼がまだ昼としての終わりを告げたわけでもなく、夜が夜として完全に始まったわけでもない、 光と闇が交錯する薄闇が支配する時間と空間があった。 その地平には、累々として立ち並ぶ多種多様の墓石が一面に広がり、 彼方の日没の一線まで果てしなく続いていた。 生を持って蘇ることは決してないが、厳然と子孫のなかに因習として存在する、 無限数の祖先という死者が眠り続けているのだった。 その窓辺にたたずんで、小夜子は、茫然とした面持ちで光景を眺め続けていた。 生まれたままの優美な全裸を麻縄で後ろ手に縛られ、綺麗なふたつの乳房には上下から挟まれた胸縄を施され、 艶やかな首筋から縦へ下ろされた縄がそれらを締め上げて、愛らしく突き出すような具合にされていた、 縦縄は、さらに、艶めかしい腰付きの女らしい曲線をあらわすくびれへ巻き付けられて、 可愛らしい臍のあたりから、なめらかな下腹部へ向かって下ろされているのだった、 その縄を掛けた女性が<私との離れられない結び付き>と言った、 思いの込められた股縄が漆黒の艶やかな恥毛を分け入って、女の割れめ深くへと埋没させられているのであった。 望むと望まないに関わらず、全裸を緊縛された縄は、 官能を煽り立てられる思いへと向かわせるものでしかなかったのだった。 小夜子の美しい顔立ちが茫然としているようであったのも、 ただ、相手からされるがままになることに、少しでも、かたくなになることができたら、という女の意地…… ささやかな抵抗のあらわれであったのだった。 だが、高ぶらされる官能の甘美に疼かされる浮遊は、眺めている広大な墓地に幻像さえ見させるものがあった―― ふたりの全裸の男は、抱きかかえた緊縛の女の生まれたままの裸身を彼方の日没の一線へ向けて運んでいた、 ゆっくりとした足取りで、黄昏の薄闇のなかを歩き続けていくのであった、 それは、長い、長い、長い時間を遡及する運行であったかもしれないし、 或いは、死者が執り行う行為としては、 一瞬のうちに空間を移動するようなものであったかもしれなかった…… やがて、広大無辺の墓地を抜けた先へ、その姿は消えていくのだった―― 「……小夜子さん、何がご覧になれて?」 彼女を緊縛していた縄尻を取る女性が優しく問い掛けていた。 小夜子は、すねて見せるように、振りかえることもせず返事もしないで、墓地の光景を眺め続けているだけだった。 「私と行ったこと、後悔なさっているの? でも、そうなることは、必然ではなかったのかしら? あなたと私は、すでに出会ってしまったのですから……」 小夜子は、緊縛で突き出させられた華奢な肩越しに、おもむろに振り返った。 そこには、顔立ちが恐ろしく自分と似ている相手が黒眼がちの深い陰翳のあるまなざしで見返しているのだった。 |
☆NEXT ☆BACK ☆権田孫兵衛老人のアンダーグラウンド タイトル・ページ |